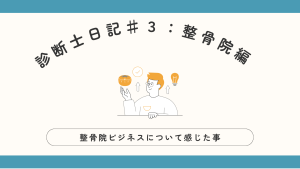診断士日記 #4 商品開発&終売編
こんにちは、福岡県で中小企業診断士として活動している 田中 きょういち と申します。どうぞよろしくお願いします。
先日、福岡県にある食品製造・卸業の会社様の経営診断の仕事に参画しました。
今回のブログは、新商品の開発と終売(販売終了)について感じたことを綴ってみます。
新商品の開発について
セブン・イレブン・ジャパンを設立された鈴木敏文氏の著書「売る力」心をつかむ仕事術はとても有名なビジネス書なので、お読みになった方も多いと思います。その中に、次のような印象的な文章があります。
“たとえば、食べものの場合、お客様は、おいしいものを出さないと買ってくれません。しかし、「おいしいもの」にはもう一つの裏返しの意味があって、それは「飽きる」ということです。”
売り手は、苦労して美味しい食べものを開発しますが、お客様はやがて飽きていやになってしまう。しかもお客様は“おいしいものほど飽きる”という矛盾。
“おいしいがゆえに飽きられる。飽きられてから次の商品を開発するのではなく、飽きられたときにすぐ次の商品を投入できるように、いまから研究に着手させたのです。”
だから、メーカーは次から次に新商品を開発しなければならない、という宿命を負っているという訳です。
メーカーは、取引先のスーパーからも、季節ごと、あるいはキャンペーンのために新商品開発の要望を受ける、ということもあるかもしれません。
では、どのようにして新商品を開発するのか。
鈴木敏文氏は、大ヒット商品の「金の食パン」の開発について、「売る力」の中で次のように記されています。
“既存の商品を多少改良した程度のA´の商品ではなく、明らかに異なるBという商品だからヒットしたのでしょう。”
“セブン‐イレブンの場合、創業以来、他社のものまねは絶対しませんでした。わたしは一時、社員たちに「他店見学をしてはならない」と命じたこともあります。”
また鈴木敏文氏は、アイドルグループAKB48の総合プロデューサーとして有名な秋元康氏から聞いた「ココアとバターと文庫本」の話からインスピレーションを得て、
“新しいものを生み出すという意味のイノベーション(革新)には二つあって、一つはこれまで存在しなかった概念のものを生み出すことです。そして、もう一つは既存の概念のものに新しい意味をつけ加えて革新することです。セブン‐イレブンの創業は前者であり、金の食パンは後者でしょう。”と綴っていらっしゃいます。(とてもホッコリするお話なので、ご興味がある方は原本をお読みください。)
(以上“ ”内は「売る力」より引用しました。)
単純に、業務計画の一環として日配商品の商品ライフサイクルを数週間、数ヶ月という短い期間設定して新商品開発を図る、ということではなくて、経営者を含めた社員全体が、そうあらねばならない必然性を認識して新商品の開発に当たることが必要、ということでしょうか。
商品の終売(販売終了)について
私はセブン‐イレブンで以前販売されていた「カスクート」というパンが大好きで、棚にあったら必ず買っていました。でも、突然店頭から消えて、それからはパン屋で「カスクート」(少し値段が張りましたが、)買うようになりました。呪術廻戦というアニメのなかで、似たようなエピソードがあったので(七海建人の回想シーン)、同じ経験をした人も結構いるのだろうと思いました。
新製品は次々に登場します。従って販売実績に基づいた判断、棚効率の最適化、新商品との競合による見直しにより、お客様に惜しまれながらも終売になる商品は必ず生まれます。
量販店やコンビニの商品終売(販売終了)のルールについて
量販店やコンビニには、商品の終売や販売終了に関して「3分の1ルール」や「2分の1ルール」といった業界慣行があります。
たとえば、「3分の1ルール」の場合、製造日から賞味期限までの期間を3等分し、納品期限・販売期限・賞味期限を設定するものです。これにより、一定期間を過ぎた商品は販売終了・廃棄となります。
食品ロス削減のため、常温加工食品や一部商品では「2分の1ルール」(納品期限を賞味期限の半分まで延長)を導入し、販売可能期間を長くしています。販売終了や取扱い終了が決定した商品は、公式ホームページの「商品のご案内」からも削除されます。
商品の終売が決定した場合、ベンダー(メーカー)には「推奨取り消し案内」が3週間前に通知され、以降は納品を停止できる運用に変更されます。これにより、センター在庫や返品ロスの削減を図ることが可能です。
食品製造業の商品終売(販売終了)のルールについて
食品製造業の場合、終売に当っては次のような観点やルールによって決定します。
【売上・利益の低下】
- 一定期間(例:6ヶ月〜1年)の売上が目標を大きく下回っている。
- 粗利益率や営業利益が基準を満たしていない。
【市場・顧客ニーズの変化】
- 消費者トレンドとのズレ(例:健康志向化で油分の多い商品が敬遠される)。
- 類似商品の競合によるシェア喪失。
- 食品表示法、アレルゲン表示、輸入規制などの変更によって継続が困難。
- 原材料の供給難・価格高騰・安全性の問題。
- 導入期→成長期→成熟期→衰退期の末期にある商品。
- 長期的な販売戦略上の入れ替え対象。
【ブランド・ポートフォリオの整理】
- 商品ラインアップのスリム化(SKU削減)。
- 同一ブランド内でのカニバリゼーション(内部競合)対策。
注意すべきポイントは、以下の通り。
- 「潜在的なニーズ」がある場合もあるので、営業担当の声を重視すること。
- 特定の小売り専売品は簡単に終売ができない。取引先の事情を配慮すること。
- 中長期戦略と整合性を取る必要があり、短期的な数値だけで判断しない。
まとめ
新商品の開発と終売(販売終了)については、経営者の経験と勘で決定してしまうことが、一番危険だと感じました。
また、最初に触れた鈴木敏文氏の著書「売る力」心をつかむ仕事術は、とても読みやすく、また示唆に富んだ秀逸なビジネス書です。まだ、読んだことがない方は、是非一読されることをお勧めします。
わたしが今回触れることが出来たのは、メーカーや量販店における新商品の開発と終売(販売終了)の一面でしょう。このブログをお読みいただいた方で、こんな事もあるよ、という事を教えて頂ける方がいらっしゃいましたら、どうぞご意見をお寄せください。読者の方のお役に立つ情報も、きっとあるでしょうし、わたしの知識不足や勘違いをご指摘いただけるとありがたいです。
今後もいろいろなビジネスについて、現場に触れて感じたことをブログに綴っていくつもりです。どうぞよろしくお願いします。